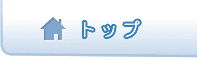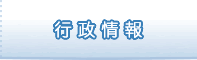トップ > くらしの情報 > 子ども・教育 > 子育て > 認可保育施設
認可保育施設
認可保育施設の概要
認可保育施設について
保護者の就労や疾病の為、昼間、家庭において十分に保育をすることができない(保育を必要とする)児童を保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。宮古島市には、公立・私立の2種類があります。
どの家庭の児童も無条件で入所できるわけではありませんのでご注意ください。
施設一覧はちらをクリック⇒ 認可保育施設一覧
令和7年度 認可保育施設空き状況はこちら➡※令和8年1月末時点※![]()
令和8年度 認可保育施設空き状況はこちら➡※1次調整後時点(令和8年1月20日時点)※![]()
施設の詳細についてこちらもご覧ください⇒わくわく子育てブックHappy
小規模保育施設について
定員が少人数(6~19人)で満3歳未満の子どもを対象にした保育施設です。3歳児クラスからは希望する保育施設への申込みが必要です。
保育士の配置人数等の違いでA型とB型に分類されます。
A型:保育従事者が全員保育士
B型:保育従事者の半数以上が保育士
家庭的保育施設について
定員が少人数(5人以下)で3歳未満の子どもを対象にした施設です。3歳児クラスからは希望する保育施設への申込みが必要です。
公私連携型保育施設について
公私連携型保育施設とは、市が事業経営者(社会福祉法人)と必要な設備と貸し付け等、協力に関する基本的事項の協定を結び運営を行う民設民営の保育施設です。
認定こども園について
幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持った施設です。宮古島市では公立認定こども園3園、私立認定こども園5園があります。認定こども園利用には、教育のみを希望する場合(1号認定)と教育と保育を利用する場合(2・3号認定)があります。私立認定こども園の1号認定の申込みや問い合わせ先は、直接各園へお問い合わせください。
入所対象となる児童について
- 宮古島市に住所を有している
- 保護者(18歳以上64歳以下までの同居者を含む)が保育の要件に該当する
- 0歳(おおむね3ヶ月)〜5歳までの集団保育が可能な児童 ※受入年齢は園によってことなります。
※支援の必要な児童の保育については、審査会で検討された状況に応じて入所調整を行います。
審査会とは・・・心身に心配事があったり困り感があるお子さんに対して、学識経験者(医師や発達支援の専門職など)の委員の意見を伺いながら、(1)集団保育が適当であるか(2)どのような支援が必要かなどについて判断するために行うものです。
| 審査会申込書類 | |
| 障がい児等保育審査会申出書 | 様式 |
| 発達のようす | |
| 意見書(医療機関用・利用施設用の2つ) | |
| 保護者アンケート | 様式 |
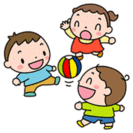
保育の要件について
保護者は下記のいずれかの要件に該当していることが必要です
| No. | 保育の要件 | 保護者の状況 | 保育実施期間 | 保育必要量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 就労 | ひと月において64時間以上労働することを常態としていること。 | 就労期間中 |
標準時間 (120時間以上就労) 短時間 (120時間未満就労) |
| 2 | 妊娠・出産 |
妊娠中、または出産後の休養が必要であること。 |
産前3ヶ月 産後6ヶ月 |
標準時間 (産後は求職活動3ヶ月を含む) |
| 3 | 疾病・障がい等 | 保護者が病気やケガ、または心身に障がいがる。 |
保護者の 療養期間中 |
短時間 |
| 4 | 看護・介護等 | 親族を介護または看護している。 |
親族の 療養期間中 |
短時間 |
| 5 | 災害復旧等 |
災害の復旧にあたっている。 (震災・火災・風水害等) |
災害復旧に要する期間 | 標準時間 |
| 6 | 求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること | 90日間 | 短時間 |
| 7 | 就学 | 大学や職業訓練校・専門学校等に通っており、ひと月において64時間以上就学していること |
就学期間中 ※職業訓練期間に求職活動期間(90日間)を含む |
申請内容により判断 |
| 8 | 虐待・DV | 虐待やDV(家庭内暴力)のおそれがある。 | 必要な期間 | 標準時間 |
| 9 |
その他 |
市長が必要と認めるとき。 |
必要な期間 |
申請内容により判断 |
※上記の要件に該当しない場合、又は要件に該当しているが定員に余裕がない場合は利用できません。 ※一度認定されても上記の要件が変更となった場合は、変更申請が必要です。 ※保育料・保育時間変更は月途中の変更はできません。→→教育・保育給付認定通知書の有効期間について![]()
育児休業について
| 保育の要件 | 保護者の状況 | 保育実施期間 | 保育 必要量 |
| 育児休業 | 育児休業取得時に既に認可保育施設を利用している児童がおり、継続利用が必要であると認められること。 | 育児休業対象児童が1歳6ヶ月になる月の末日まで | 短時間 |
※新規申込に育児休業要件は該当しません。 ※育児休業対象児童の入所が決定した場合は、入所後1ヶ月以内に復職することが条件となります。
提出書類について
- 提出する書類の有効期限は、証明日から(記入日)から3ヶ月以内となります。
- きょうだい同時で申込む場合は、申込人数分(部数)の書類の提出が必要です。書類は、1部を原本、他はコピーで対応できる書類もあります。
- 提出書類は、各世帯の状況で変わりますので『提出書類一覧』からご確認ください。 ⇒ 提出書類一覧
保育料について
保育料の決定時期
保育料は、保護者の市民税課税額(所得割)により、保育料徴収基準額表に基づいて算定されます。
※ただし、同居の祖父母等が生計の中心者の場合は祖父母等も含む場合があります。
◆保育料を決定する市民税課税額(所得割)は、配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除などの適用を受ける前の金額となります。
◆市民税課税額(所得割)が確認できない世帯(未申告・税の証明の提出がない方等)は、第8階層の保育料(最高額)になり、多子世帯の軽減措置等受けられません。ご注意ください。
◆扶養に入っている方でも所得の申告は必ず行ってください。
◆宮古島市に転入予定の方は、1月1日に住所がある市町村において、所得の申告を必ず行ってください。
◆海外に住んでいた方は、1年間の収入等が確認できる書類を提出してください。外国語で記載されている証明書類については和訳の提出が必要です。
◆令和元年10月より幼児教育・保育の無償化の制度により3歳児クラスから5歳児クラスの児童の保育料が無料となります。
保育料を決定するための税資料の提出が必要な方
マイナンバーの申出により省略することができます。ただし、必要に応じて提出をお願いする場合があります。
令和7年1月1日に宮古島市外に住民票のあった方(令和8年4月〜8月入所の方)
『令和7年度所得課税額証明書(所得・控除・課税額が記載されているもの)』を転入前の市町村から取り寄せて提出していただく場合があります。
令和8年1月1日時点で宮古島市以外に住民票がある方(令和8年9月〜令和9年3月入所の方)
『令和8年度所得課税証明書(所得・控除・課税額が記載されたいるもの)』を転入前の市町村から取り寄せて提出していただく場合があります。
保育料の切り替え時期
市民税の賦課決定が6月になっていることから、毎年4~8月は前年度の市民税課税額、9~3月は当年度の市民税課税額に基づいて保育料が決定されます。保育料決定後に課税額の変更があった場合は、こども未来課までご連絡ください。

※前年度の市民税が変更になった場合は4月まで、当年度の市民税が変更になった場合は9月まで遡及します。
多子世帯の保育料について
同一世帯で入所児童が2人以上の場合は、第1子は基準額の全額負担、第2子は半額負担、第3子以降は無料となります。
また、年収約360万円未満相当の世帯については、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢が撤廃され、第2子を半額、第3子以降は無料となります。
また、年収360万円未満相当のひとり親世帯・障がい世帯等の場合は、第2子以降は無料となります。
★宮古島市単独の多子軽減措置事業について★
同じ世帯に中学3年生以下の子が4人以上いる場合は認可保育園等に通っているお子さんの保育料が無料となります。
※軽減措置を受けるためには申請が必要となります。
申請された翌月の保育料から減免の対象となります。遡って保育料を軽減することができません。
こども家庭局 こども未来課
電話:0980-79-7825 FAX:0980-73-1984