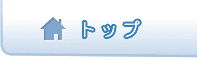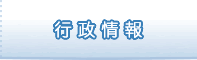トップ > くらしの情報 > 国民健康保険・国民年金 > 国民健康保険 > 高額療養費
高額療養費
高額療養費制度とは
医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
高額療養費制度についての詳細は、厚生労働省HPをご参照ください。高額療養費制度を利用される皆様へ![]()
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
| 所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
| 901万円超 | ア |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% |
140,100円 |
| 600万円超~901万円以下 | イ |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% |
93,000円 |
| 210万円超~600万円以下 | ウ |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% |
44,400円 |
| 210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 |
24,600円 |
◆ 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
◆ 4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
70歳~74歳未満の人の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
| 現役並所得者 |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% ●4回目以降(※)は140,100円 |
|
|
課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% ●4回目以降(※)は93,000円 |
||
| 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% ●4回目以降(※)は44,400円 |
||
|
一 般 |
18,000円 (8月〜翌年7月の年間限度額は144,000円)* |
57,600円 ●4回目以降(※)は44,400円 |
|
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | |
※ 4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
* 低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の自己負担額も対象です。
◆ 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
〇年齢別計算方法〇
|
同一世帯で 70歳未満の人を 合算して限度額を超えた場合 |
同一世帯で、同じ月内に70歳未満の人が21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して70歳未満の人の限度額を超えた分が支給されます。 |
|
同一世帯で 70歳以上で75歳未満の人を 合算して限度額を超えたとき |
同一世帯で、入院外来、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して、70歳以上75歳未満の人の限度額(世帯単位)を超えた分が支給されます。 |
|
同一世帯で 70歳未満の人と 70歳以上75歳未満の人を 合算して限度額を超えるとき |
70歳以上75歳未満の人の限度額を適用後、70歳未満の21,000円以上の自己負担額を合算して、70歳未満の人の限度額を超えた分が支給されます。 |
※1)入院時の食事代の標準負担額や、差額ベット料、保険診療の対象外となるものは除きます。
※2)同じ病院・診療所でも、外来と入院は別計算になります。
※3)同じ病院・診療所でも、歯科は別計算になります。
高額療養費の払い戻し(高額療養費支給申請)について
医療費の支払いが、1か月当たりの自己負担限度額を超えた世帯には、「高額療養費支給申請のお知らせ」を送付しています。該当のお知らせハガキがご自宅に届いてから支給申請を行ってください。申請手続きについては、宮古島市役所国民健康保険課窓口での受付とさせていただきます(※各地区(平良・城辺・下地・上野・伊良部)ごとの受付は終了しております。ご了承ください)。また、手続きをする際には、下記のものをそろえてお持ちください。
手続きに必要なもの
□ 「高額療養費支給申請のお知らせ」ハガキ
□ 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
□ 医療機関から発行された入院分領収書
□ 世帯主名義の金融機関口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
□ 印鑑(認印)※シャチハタ不可
□ 世帯主と受診した方のマイナンバーカード、またはマイナンバーがわかるもの
限度額適用認定証について
入院等で医療費(保険適用分のみ)が高額となる場合、あらかじめ限度額適用認定証(住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は限度額適用認定・標準負担額減額認定証)を申請し、交付を受けて医療機関等で提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
申請に必要なもの
□ 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
□ マイナンバーのわかるもの(対象者・世帯主)
※保険税を滞納していると交付を受けることができません。
※70歳以上75歳未満で、所得区分が現役並みⅢの方と一般の方は、被保険者証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため、限度額適用認定証の交付申請は不要です。
また、オンライン資格確認を導入している医療機関等において、マイナ保険証を提示し限度額情報の提供に同意いただくことで、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます(限度額適用認定証の事前申請は不要となります、マイナ保険証をぜひご利用ください)。
利用方法についてはこちら マイナンバーカードを健康保険証として使うには![]() (1289KB)
(1289KB)
オンライン資格確認が利用できる医療機関についてはこちら![]() をご参照ください。
をご参照ください。
マイナンバーカード健康保険証利用登録に関する問い合わせ先
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
※音声ガイダンスにしたがって「4→2」の順に進んでください。
マイナンバーカード健康保険証利用登録についてはこちら![]() もご確認ください。
もご確認ください。
高額療養費貸付制度
宮古島市の国民健康保険に加入している方で、1か月にかかる医療費(一部負担金)が高額になり支払いが困難な場合には、高額療養費貸付という制度があります。
申請すれば、宮古島市から医療機関へ直接貸付金を支払うため、被保険者(患者)は自己負担限度額のみを医療機関へ支払っていただくだけで済みます。
貸付金の返済は、高額療養費を本人へ支払わず、本市が貸付金へ充当することにより終了します。
下記の場合にあてはまる方は、一度お問い合わせください。
□ 継続的な治療・投薬等が必要で、外来でかかる医療費が限度額を超えると見込まれる場合
□ 手術を伴う入院等で高額な医療費を請求されたが、支払いが困難な場合(限度額適用認定証の交付を受けていない場合)
□ 入院した際の医療費について、限度額適用認定証の交付は受けたが医療機関へ提示するのが遅れて、高額な医療費を請求された場合
□ 入院中に転院があり、それぞれの医療機関で限度額適用認定証を提示したが、1か月の医療費が通常よりも多く請求された場合(2つの医療機関から限度額適用後の入院費を請求された場合)
申請ができない場合
次の方については、この制度のご利用をお断りすることがあります。詳しくは、お問い合わせください。
□ 医療機関の了承が得られていない方
□ 世帯内に未申告者がいるため、課税状況がわからず世帯区分を判定できない方
□ 保険料に未納・滞納がある方
手続きに必要なもの
□ 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
□ 請求書(医療機関発行)
□ 印鑑(認印)※シャチハタ不可
※ 対象は医療機関ごとになりますので、たとえば2つの医療機関で利用される場合は、申請書は2枚必要になります。また、同じ医療機関でも、入院と外来の両方で利用される場合も申請書は2枚必要になります。
※ 請求の時効は受診した月の翌月の1日から起算して2年間です。申請が遅れると支給ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。
対象期間(8月1日〜翌年7月31日)を通して宮古島市国民健康保険に加入していた世帯のうち、条件に該当してる世帯には市より支給申請案内書類を送付します。
※世帯で、医療・介護いずれかの負担額がない場合には支給対象とはなりません。
| 所得区分 | 限度額 | |
| ア | 所得901万円超 | 212万円 |
| イ | 所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
| ウ | 所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
| エ | 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
| 所得区分 | 限度額 |
| 現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 |
| 現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 |
| 一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 |
| 低所得者Ⅰ | 19万円 |
※低所得者Ⅰで介護サービス利用者が複数いる世帯については、合算限度額19万円が高額介護サービス費等の限度額を下回る事態が生じることから、医療保険者が原則どおり低所得Iの合算限度額19万円により医療保険分の支給額を計算した後、介護保険者が低所得Ⅱの合算限度額31万円により介護保険分の支給額を計算します。
特定疾病療養受領証
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、特定疾病療養受領証」を医療機関などの窓口で提示すれば、自己負担額が1つの医療機関で1か月に1万円(上位所得者のいる世帯の70歳未満の方は2万円)までとなります。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
◆ 先天性血液凝固因子障害の一部
◆ 人工透析が必要な慢性腎不全
◆ 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
□ 対象者の資格確認書または資格情報のお知らせ
□ 医師の意見欄を記入した国民健康保険特定疾病認定申請書
□ マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの
市民生活部 国民健康保険課 庶務給付係
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974