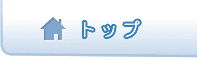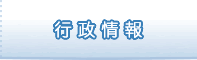トップ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 障害福祉 > 知的障害について
知的障害について
療育手帳について
概要
知的障害の方に対して交付されます。一貫した相談および、諸サービスが受けられます。
療育手帳制度は、知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談が行われるようにするとともに、各種の援助措置を受けやすくするために手帳を交付し、知的障害児(者)の福祉の増進を図る制度です。
障害の程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)と表示されます。この制度に関連する援助措置があります。
療育手帳の申請に必要な書類
1.療育手帳交付申請書
2.生育歴(用紙は障がい福祉課窓口にあります)※母子手帳等をみて記載をお願いします
3.印鑑(認印可)
4.顔写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ)
※代理人申請の場合は代理人の身分証を持参ください
事務の流れ
本人(保護者)申請→障がい福祉課受理→(18歳未満)県中央児童相談所・(18歳以上)知的障害者更生相談所 判定
→障がい福祉課にて手帳交付
※県中央児童相談所および知的障害者更生相談所の判定は県より派遣されるため、年2〜4回です。
再判定の電子申請の開始について
療育手帳交付後の18歳以上の方の再判定の申請について、沖縄県公式ホームペーシからオンラインで申し込みが可能となりました。
その他福祉サービスについて
1.重度心身障害者(児)医療費助成制度について
概要
重度の障がいのある方が、病気やケガで治療を受けた際、医療費の自己負担分、入院費の食事費の半額を助成します。
※所得制限が定められていますので、一定所得以上があった年度は支給停止となります
対象となる方
宮古島市在住の方で、以下のいずれかに該当する方
○身体障がい者:身体障害者手帳の等級が1級もしくは2級のもの
○知的障がい者:療育手帳がA1またはA2のもの
申請に必要なもの
●受給資格者申請書![]() (88KB) ●身体障害者手帳もしくは療育手帳の写し ●印鑑 ●本人名義通帳の写し ●健康保険証
(88KB) ●身体障害者手帳もしくは療育手帳の写し ●印鑑 ●本人名義通帳の写し ●健康保険証
※転入の方は同一世帯全員分の所得・課税証明書が必要になる場合がございます
医療費の申請方法
【自動償還(じどうしょうかん)】
医療機関等の窓口で「重度心身障害者医療費受給資格者証」「保険証」を提出し、医療費の自己負担分をお支払いただきますと、後日口座振込により助成金が支払われます。※対応していない医療機関もございます
【償還払い(しょうかんばらい)】
自動償還対応外の医療機関を受診した際、または県外の病院を受診した際、以下を持参し障がい福祉課及び伊良部・城辺・下地・上野各出張所にて申請を行ってください。
①「重度心身障害者医療費助成受給資格者証」 ②領収書 ③印鑑
④宮古島市重度心身障害者(児)医療費助成申請書![]() (76KB)(窓口にもあります)
(76KB)(窓口にもあります)
受給者証の更新について
受給資格者証は毎年更新しています。(自動更新)毎年8月1日〜翌年の7月31日までの期間となっております。
受給者本人及びその配偶者と同一世帯内の扶養義務者の所得状況を確認のうえ、所得制限限度額以内の方には7月下旬ごろに新しい受給者証を郵送にて送付いたします。※所得制限限度額超過の方には、その旨通知を送付いたします。
所得状況の確認が出来ない場合
所得状況の確認にあたって、「未申告」の方や「転入」の方などは、本市で所得状況の確認が出来ません。
別途、提出書類が必要になる場合がございます。
2.特別児童扶養手当の支給
20歳未満の最重要度、重度、又は中度の障害のある児童を養育する父又は母(父又は母がいない場合はそれに代わる養育者)に支給されます。
3.特別障害者手当等の支給
在宅の最重度および重度の方に月一定額の手当が支給されます。
4.障害基礎年金の支給
20歳以上の最重度および重度の方が支給の対象です。
5.重度障害児日常生活用具の給付等
在宅の最重度および重度の方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具が給付、貸与されます。
6.心身障害者扶養共済制度
障がい者の扶養者を加入者とし、毎月一定額の掛け金を納入する制度です。加入者が死亡、又は重度障がい者となった場合、残された障がい者に毎月一定額の年金が給付されます。
7.知的障害者相談員
知的障害者相談員が設置されており、各種の相談に応じます
8.所得税・地方税の控除および減免
障害の程度のい応じて、所得税・地方税(県民税、市町村民税、自動車税、軽自動車税)に控除および減免があります。
9.NHK受信料の減免
最重度および重度の方のいる低所得世帯(市町村民税非課税世帯)は、受信料が減免になります。
10.公営住宅の優先入居
障がい者がいる世帯の入居希望を配慮することになっています
11.運賃割引制度
バス、鉄道、飛行機などの運賃が割引になります。航空運賃は満12歳以上の知的障がい者が対象。